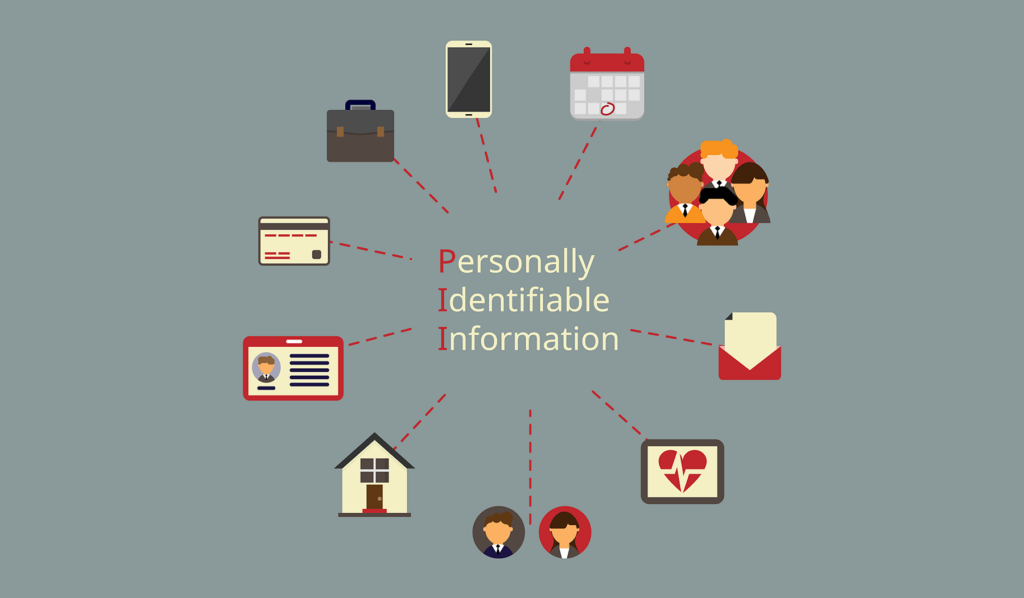構成管理とは? 構成管理の目的と効率的に実現する方法
ビジネスにおけるIT活用は欠かせないものとなり、企業内にはさまざまなシステムが導入されています。利用者の利便性は向上する一方で、利用するアプリケーションやデバイスは増加、システムの連携により構成は複雑化するなど、運用担当者の管理業務は増大しているのではないでしょうか。システムの安定稼働と管理業務の負荷軽減を実現するには、適切な構成管理を行うことが効果的です。本記事では、構成管理の概要やメリット、効率化するポイントについて解説します。
目次
構成管理とは
構成管理とは、企業のITリソースとサービスを制御するためのガバナンスおよびエンジニアリングプロセスを指します。構成管理が適切に行われていれば、組織はシステムがどのように構成され、それぞれの要素がどのように相互に関連しているかを把握することができます。具体的には、企業内のITサービスを構成しているハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、ライセンス、保守契約などの情報を洗い出し、常に最新の情報となるように管理します。
構成管理の必要性
構成管理を行わない場合、組織全体のハードウェアやソフトウェアの構成に関して信頼できる情報源がないため、業務上のさまざまな非効率とリスクを招くことになります。
例えば、影響範囲の広い重大な脆弱性が発見されたときに、もし自社のシステムを構成する要素や正確なバージョンなどが管理されていなければ、環境の調査から行う必要があるため多くの労力と時間がかかります。あるいは、特定のソフトウェアのアップデートを行ったら、一部の環境はOSが古いために対応しておらず、ソフトウェアが動かなくなってしまったというようなケースもあるでしょう。
ITサービスの安定稼働、業務効率化、セキュリティの保護、コンプライアンスの遵守などを達成するために、構成管理が必要だといえます。
IT資産管理との違い
IT資産管理と構成管理では管理する対象・範囲に大きな違いはありませんが、主となる目的が異なります。構成管理はITサービスをトラブルなく提供し続けることを目的とするのに対し、IT資産管理は財務上の管理や法令・コンプライアンスの遵守を目的とします。具体的には、IT資産管理では財務諸表へ記載するための資産の棚卸し、ライセンス違反の防止、リース契約や保守契約の管理などを行います。これらにより、IT資産の有効活用とコスト最適化、作業の効率化などを目指します。
構成管理の対象要素
具体的に構成管理の対象となる主な要素について解説します。以下の情報は収集後に変更が生じたらすぐに更新し、常に最新の正確な状態を保っておくことが重要です。
ハードウェア
PCやサーバー、周辺機器など物理的な資産についての情報です。
- ハードウェア機器一覧、仕様(製品名、識別番号、メーカー名、設置場所、スペック、保守情報など)
- ハードウェア構成
ソフトウェア
導入しているOSやミドルウェア、アプリケーション、ウイルス対策ソフトなどの情報です。
- ソフトウェア一覧、仕様(製品名、メーカー名、機能、設定情報、バージョン、アカウント情報など)
- ソフトウェア構成
ネットワーク
物理的なネットワーク機器や社内ネットワーク全体の構成、回線などについての情報です。
- ネットワーク機器一覧、仕様(製品名、メーカー名、製品スペック、設定情報など)
- ネットワーク接続構成
- ネットワーク回線一覧(回線名、回線速度、起点・終点情報など)
契約情報
システムに関する契約情報です。
- 保守契約情報(問い合わせ先情報、契約番号、契約期間、契約内容など)
- ライセンス情報(ライセンス内容、期限、利用者管理など)
ベンダー情報
システム構築や運用に複数のベンダーが関わっている場合に、各要素とベンダーを紐付けるための情報です。
- ベンダー一覧(各ベンダー名、担当領域、担当者名、連絡先など)
構成管理を行うメリット
構成管理を行うことによって得られる具体的なメリットについて解説します。
システムの安定稼働を実現
システムの構成要素を正確に把握することは、システムの安定稼働の基礎となります。システムのバージョンアップや設定変更を行うことにより、周辺機器や連携システムに不具合が生じるケースも多いです。そこで、ソフトウェアやシステム間の依存関係などを把握しておくことで、変更による影響も予測が立てやすくなります。構成管理を通じて環境を整えることで、ITシステムの品質・信頼性を高め、安定稼働を実現できるでしょう。
業務負荷の軽減と効率化
きちんと構成管理を行い、要素や全体の構成を可視化しておくことは業務負荷の軽減につながります。構成を確認できるドキュメントや管理方法が確立されていないと、何かシステムに変更を行う際などに、構成する要素や影響範囲を都度手動で調査する必要が生じてしまいます。機器やライセンスなどの調達、更新、破棄のライフサイクルの管理や、パッチ適用などの運用業務を効率化するためにも、構成管理は有効です。
セキュリティの強化
脆弱性は日々発見され、業界団体やベンダーから公開されています。しかし、脆弱性に対応するためには、脆弱性が発見されたソフトウェアのバージョンや危険性、影響範囲などを把握し、自社システムが該当するか確認する必要がなります。その際に、システム情報を正確に把握できていれば、スムーズに判断して対処することが可能です。脆弱性情報の発表から修正するまでの間を狙ったサイバー攻撃が増加しているため、セキュリティの観点からも構成管理の重要性が高まっています。
脆弱性の対応、管理についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
脆弱性管理はなぜ必要? 脅威から保護するための実施方法やポイントを解説| ベアケアブログ
コンプライアンスの遵守
コンプライアンスとは、規格の制定や認定を行う標準化団体や、政府、業界団体などによって確立されたガイドラインを遵守することです。組織全体のITシステム、ITインフラの構成を管理し、監査できる仕組みを導入することは、組織のコンプライアンスへの取り組みをサポートできます。その他にも、ソフトウェアライセンスの不正利用を防ぐことで、ライセンス違反による損害賠償、社会的な信用の失墜などを予防できます。
構成管理を効率的に行うポイント
構成管理はExcelなどを使用して手作業で行うこともできますが、ミスの可能性やドキュメントの更新にかかる時間が逆に業務を圧迫することがあります。効率的に構成管理を行うためには以下を検討するのがおすすめです。
ツールを活用する
構成管理を効率化するにはIT資産管理ツールや統合運用管理ツールを活用するのがおすすめです。IT資産管理ツールはIT資産を一元的に管理するため、そのデータを利用して構成管理ができます。IT資産管理に加えて、インベントリ収集、デバイス制御、セキュリティパッチ管理、リモートコントロール、操作ログ管理などといった機能を備えているツールもあります。これらのツールを活用すれば手作業よりも正確かつ効率的に構成管理ができます。
IaCを導入する
IaC(Infrastructure as Code)とはITインフラの構成や設定を再現可能な形でコード化して自動化する仕組みです。従来のインフラ管理とは違いIaCではコードでインフラを管理するため、Gitなどのツールでバージョン管理ができるようになります。作業履歴も確認できるため、インフラをIaC化することできれば管理やメンテナンスがしやすくなります。特に、何度も同じ構成の環境を用意する必要があるような場合は効力を発揮します。
アウトソースを検討する
手間と時間のかかる構成管理は専門業者にアウトソースするのも有効な手段です。構成管理ツールの導入や構成管理データベースの構築、現状の情報収集などを依頼できます。プロの視点からアドバイスをもらえるサービスなどもあり、高品質なサービスによるIT環境の継続的な改善も期待できるしょう。
まとめ
複雑化するシステムを安定稼働させるには構成管理が必要不可欠です。ほかにもセキュリティの強化や障害発生時のスムーズな対応、業務負荷の軽減などさまざまなメリットがあります。 しかし構成管理を行うには手間や時間を要するため、逆に業務を圧迫しかねない懸念もあるでしょう。そこでツールの活用やアウトソースなど、効率的な構成管理を行うため方法も併せて検討するのがおすすめです。